歯周病になりやすい人の特徴と予防法、治療費用まで解説
こんにちは。広島県広島市中区胡町、広島電鉄「胡町駅」より徒歩1分にある歯医者「南青山デンタルクリニック広島医院」です。

歯磨きをしっかりしているのに歯周病になりやすいと感じたことはありませんか。実は、歯周病は単にケア不足だけでなく、生活習慣や歯並び、全身の健康状態などさまざまな要因が関係しています。
歯周病は、日本人の成人の多くがかかっているといわれる身近な病気です。歯周病を予防するためにも、なりやすい人の特徴について理解し、ご自身に当てはまる場合は対策をしましょう。
今回は、歯周病になりやすい人の特徴について詳しく解説します。
歯周病になりやすい人の特徴

歯周病は、誰にでも起こり得る病気ですが、特定の習慣や体質によって発症リスクが高まることが知られています。自覚症状が出にくいため、気づかないうちに進行してしまうことも珍しくありません。
以下では、歯周病になりやすい人の特徴について詳しく解説します。自分に当てはまる項目がないかを確認しましょう。
喫煙習慣がある
タバコを吸う人は、歯周病にかかるリスクが非喫煙者に比べて高いとされています。これは、タバコに含まれるニコチンや有害物質が歯ぐきの血流を悪化させ、免疫力を低下させるためです。
また、喫煙者は歯ぐきの炎症や出血が現れにくくなる傾向があります。これによって、発見が遅れてしまうことも多いです。
歯並びが悪い
歯並びが悪いと、歯ブラシが届きにくい部分ができ、磨き残しが多くなってしまいます。その結果、プラークがたまると、歯周病になるリスクが高まるのです。
口腔ケアが不十分
歯みがきの頻度が少なかったり、磨き残しが多かったりすると、歯垢(プラーク)がたまり、歯周病の原因となる細菌が増殖します。
特に歯と歯ぐきの境目や、奥歯の裏側などは汚れがたまりやすく、丁寧にケアを行う必要があります。デンタルフロスや歯間ブラシを併用して、細かい部分に付着した汚れを落とすことが重要です。
糖尿病などの全身疾患がある
糖尿病と歯周病には深い関係があり、相互に悪影響を及ぼすともいわれています。
血糖値のコントロールが不安定だと、感染への抵抗力が下がり、歯ぐきの炎症が悪化しやすくなります。また、歯周病が悪化するとインスリンの働きが妨げられ、糖尿病の管理も難しくなるのです。
ストレスや睡眠不足
ストレスや慢性的な睡眠不足は、免疫機能を低下させ、歯周病菌に対する抵抗力を弱めます。また、ストレスによって歯ぎしりや食いしばりが生じると、歯ぐきに余計な負担がかかり、炎症を引き起こしやすくなります。
生活習慣の見直しやリラクゼーションを取り入れることで、歯周病予防につながります。
ホルモンバランスの変化がある
妊娠期や更年期など、ホルモンバランスが大きく変化する時期は、歯周病にかかりやすくなるとされています。女性ホルモンの影響で歯ぐきが炎症を起こしやすくなるのです。
妊娠中は妊娠性歯肉炎と呼ばれる特有の歯周病もあるため、定期的に歯科医院を受診して歯ぐきの状態を確認してもらうことが重要です。
歯周病の予防方法

歯周病は予防できる病気です。予防の基本は、正しい歯みがきと生活習慣の見直しにあります。ここでは、歯周病を予防するための具体的な方法を解説します。日常生活に取り入れやすいことから意識することで、将来的な歯の健康を守ることにつながります。
正しい方法で歯磨きを行う
歯周病予防の基本は、毎日の歯磨きにあります。
ただし、ただ磨くだけでは不十分で、正しい方法で行うことが重要です。歯と歯ぐきの境目を意識し、毛先をやさしく当てて小刻みに動かすことがポイントです。強く磨きすぎると歯ぐきを傷つけることがあるため、やさしい力で磨きましょう。
また、健康な歯ぐきであれば一般的な硬さの歯ブラシで問題ありません。歯ぐきに炎症がある場合や知覚過敏がある場合はやわらかめの歯ブラシがよいでしょう。
また、1日2〜3回、時間をかけて丁寧に磨く習慣を身につけましょう。自己流では磨き残しが多くなるため、歯科衛生士によるブラッシング指導を受けるのも効果的です。
デンタルフロスや歯間ブラシを活用する
歯ブラシだけでは、歯と歯の間や歯と歯ぐきの境目の汚れを完全に取り除くことは難しいとされています。そのため、デンタルフロスや歯間ブラシの併用が推奨されます。
毎日のケアに取り入れることで、歯周病の予防効果が格段に高まります。
定期的に歯科検診を受ける
定期的な歯科検診は歯周病の早期発見と予防に欠かせません。歯科医院では、専門的なクリーニングや歯石除去を受けることができ、セルフケアでは取り除けない汚れも効果的に除去できます。
3ヶ月から6ヶ月に1回のペースで通院することで、歯周病のリスクを大幅に減らすことができます。歯周病になりやすい人や過去に歯周病治療歴がある場合は、より短い間隔で検診を受けるのが望ましいとされています。
自覚症状がなくても定期的に受診することで、進行を防ぐことができるでしょう。
食生活を見直す
バランスの取れた食生活は、歯ぐきの健康を保つために欠かせません。ビタミンCやカルシウム、たんぱく質は歯周組織の修復や強化に役立つ栄養素です。
一方で、糖分の多い食品や間食が多いと、口腔内の細菌が活発になり、歯周病の原因となるプラークがたまりやすくなります。歯周病を予防するためには、食事の内容だけでなく、食べる時間や回数にも気を配り、口内環境を整えることが大切です。
禁煙する
喫煙は歯周病のリスク要因の一つであり、タバコをやめることで歯ぐきの血流や免疫力が回復しやすくなります。禁煙によって、歯周病の進行を食い止めるだけでなく、治療効果も高まることがわかっています。
喫煙習慣がある人は、禁煙外来などの専門機関のサポートを受けることを検討するのも良いでしょう。
ストレスを管理する
ストレスが慢性的に続くと、体全体の免疫力が低下し、歯周病菌に対する抵抗力も弱まってしまいます。さらに、ストレスによって歯ぎしりや食いしばりが起こると、歯ぐきや歯の周辺に負担がかかり、炎症が悪化しやすくなります。
例えば、1日30分程度のウォーキングや深呼吸、趣味の時間を設けるなど、自分なりのストレス発散法を取り入れ、心身の健康を整えることが歯周病予防にもつながります。
歯周病を治療する場合にかかる費用
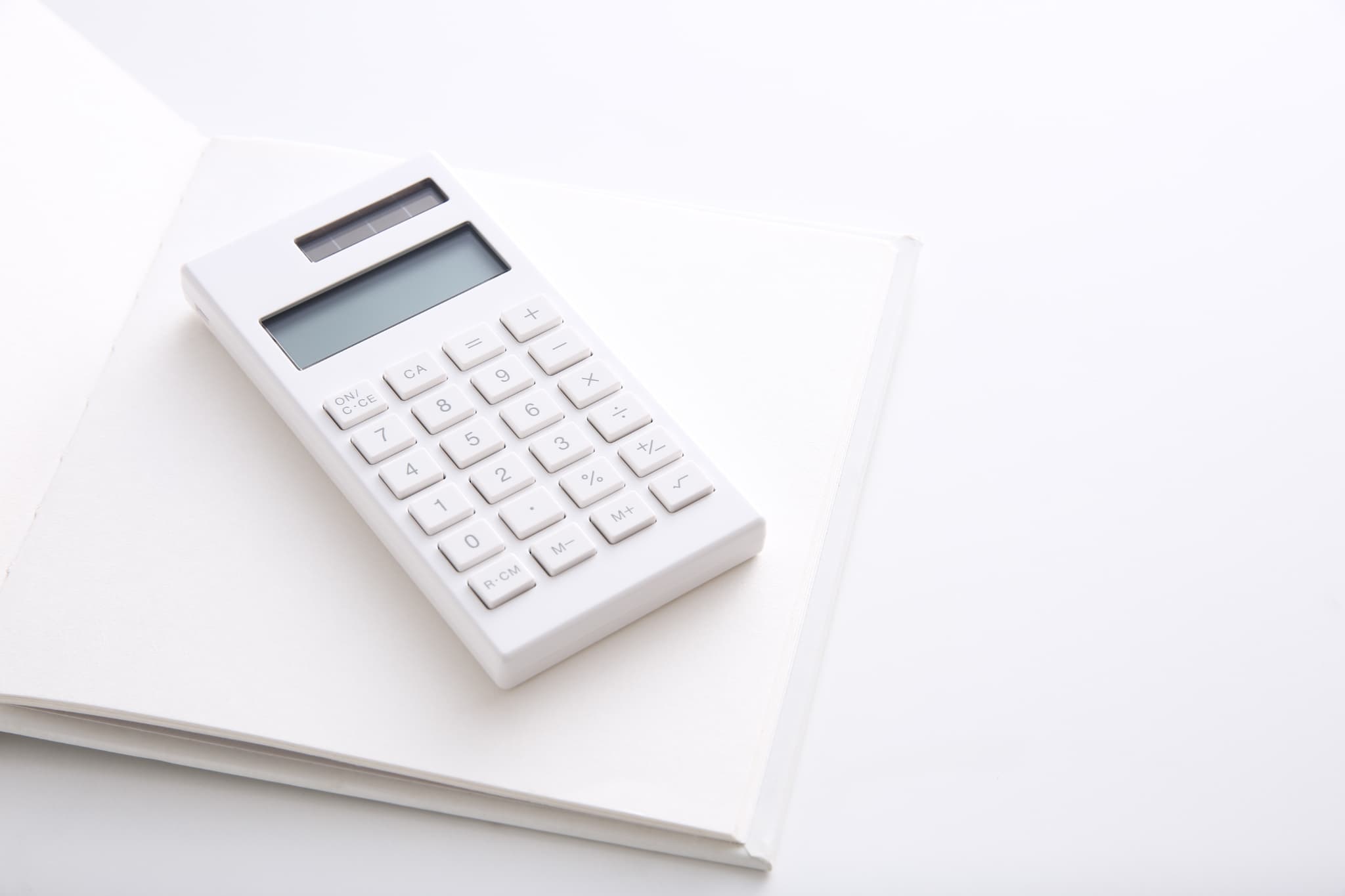
歯周病を治療する場合にかかる費用は症状や治療内容によって異なります。歯石除去やクリーニングなどの基本治療は、保険診療で1回あたり3,000円〜5,000円程度です。
中等度以上に進行すると、歯周外科治療が必要となり、1本あたり1万〜2万円前後かかることもあります。保険が適用されない場合は、10万円以上かかるケースもあるでしょう。
歯周病治療の通院頻度

初期段階の歯周病の治療であれば、1~2週間おきに2~5回程度の通院が目安とされています。これは、歯石除去や歯のクリーニング、歯磨き指導などの基本的な処置を段階的に行うためです。進行するほど通院回数は増え、治療期間も長くなるでしょう。
特に歯周病になりやすい人は、歯ぐきの炎症や歯石の付着が多いため、初期段階でしっかりとしたケアが必要です。
まとめ

歯周病、遺伝や加齢といった要因に加え、生活習慣や日々のケアによってもリスクが大きく変わる病気です。喫煙、糖尿病、ストレス、口腔ケアの不足など、さまざまな要因が複雑に関係しています。また、ホルモンバランスの変化も見逃せません。
こうした特徴に自分が当てはまるかを知ることは、予防や早期対策への第一歩です。
歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどないため、日常のケアに加え、定期的な歯科受診を習慣づけることが大切です。将来の歯の健康を守るためにも、自分自身のリスクを理解し、早めの行動を心がけましょう。
歯周病の症状にお悩みの方は、広島県広島市中区胡町、広島電鉄「胡町駅」より徒歩1分にある歯医者「南青山デンタルクリニック広島医院」にお気軽にご相談ください。
当院は、患者さまに「少しでも笑顔になってお帰りいただく」ことを意識して、病気の再発・発症の予防に努めています。マウスピース矯正やホワイトニングなど、自由診療の治療を中心に、保険診療にも対応しています。
当院のホームページはこちら、お電話による予約も受け付けております。

